with azbil
豆知識
グラム
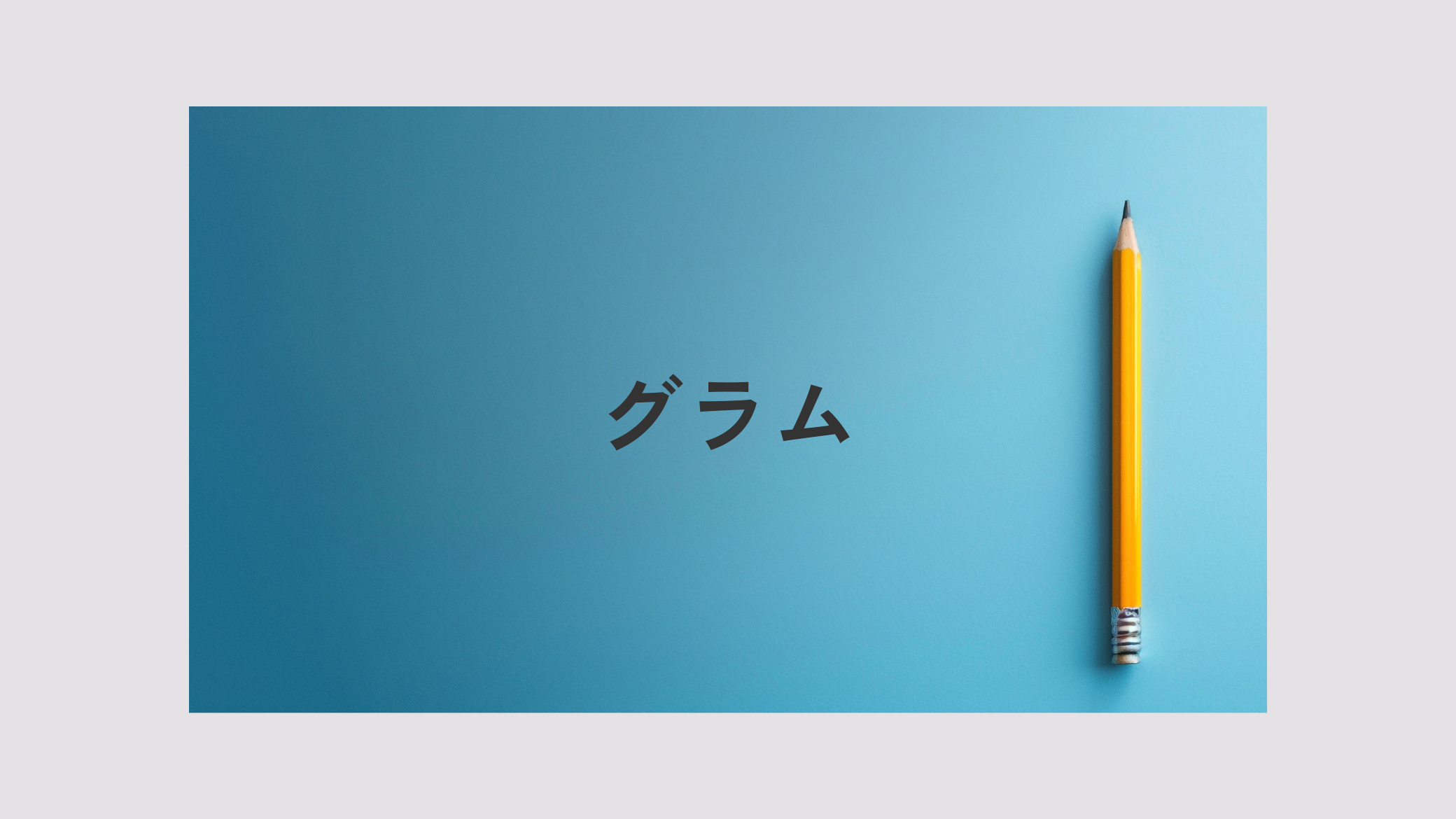
おにぎり1個が約100g、コピー用紙1枚は約4g──私たちの暮らしのなかで「g(グラム)」という重さの単位はとても身近な存在です。料理、荷物、体重計など、日常のあらゆる場面で「グラム」は使われています。

この「グラム(gram)」という言葉、もともとはギリシア語の「grámma(小さな重さ)」に由来しています。18世紀末、フランスで「メートル法」が作られたときに、グラムも重さの基本単位として導入されました。当時は「摂氏4度の水1立方センチメートルの質量」が1グラムとされており、水の重さが基準だったのです。
ちなみにキログラム(kg)はグラムの1000倍。ではその「キログラム」、つい最近まで、1個の分銅で決められていたことをご存じでしょうか?
その分銅とは、1889年にフランスで作られた国際キログラム原器というもの。白金とイリジウムでできた、直径と高さが約39mmの小さな円柱で、「これが1kgの基準です」と世界で決められていました。日本にも、この複製品のひとつ(No.6原器)があり、長年茨城県つくば市にある国立研究開発法人 産業技術総合研究所で大切に保管されています。
しかし、物は時間とともに少しずつ変わります。空気や汚れの影響で、わずかに軽くなったり重くなったりすることがあるのです。
物体に依存した基準よりは、普遍的で不変な基準が求められるようになり、2019年5月20日、キログラムの定義が130年ぶりに改定されました。分銅に代わって、新たな基準となったのは「プランク定数」という、自然法則に基づいて決められた数字です。
プランク定数は、量子力学というとても小さな世界で使われる定数です。キログラム定義の改定に先だって、世界中の研究者によってより正確な数に再定義されました。プランク定数を使うということは、「物に頼らず、数字で定義できる」という大きなメリットがあります。この改定によって、特別な装置があれば、世界中どこでも同じ1kgを再現できるようになりました。
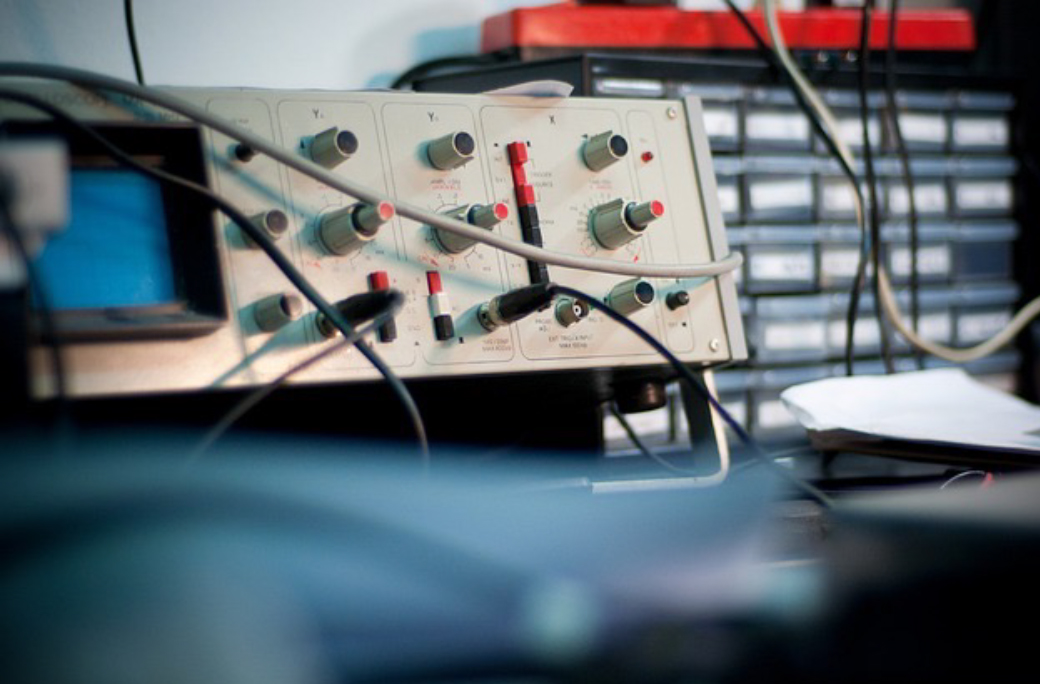
キログラムのほかにも、アンペア(電流)、ケルビン(温度)、モル(物質量)も同じように、「自然法則に基づいて決められた数字」を使って定義されることになります。こうして、長さ・時間・質量・電流・温度・物質量・光度というSI基本7単位すべてが、物に頼らず再現できる単位に生まれ変わったのです。
もちろん、私たちの暮らしで「1kgのお米」や「500gのお肉」といった表示が変わるわけではありません。ただし、医療やナノテクノロジーのような最先端分野では、ほんのわずかな重さの違いが大きな差につながることもあります。そんな場面では、より正確な定義が大きな力を発揮します。グラム(gram)は正確な計量の出発点。これまでもこれからも、科学や技術を支え続けているのです。
参照:
産総研サイエンスタウン:原器から物理定数へ!130年ぶりとなるキログラムの定義改定
産業技術総合研究所計量標準総合センター、SI単位全般及び定義の詳細「国際単位系(SI)」

 関連情報
関連情報





