with azbil
SPECIAL
- NEW
Special Talk 特別対談 | 日経BP 総合研究所ESGフェロー 酒井 耕一 氏×アズビル株式会社 取締役 代表執行役副社長 横田 隆幸

社員の自社株保有制度の拡充を推進することで
全員経営を目指し人的資本の強化を図る
人的資本の強化が企業に求められている今日、アズビルではその一環として全社員を対象とする「株式給付制度(J-ESOP-RS)」と「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」制度を導入しました。これにより、社員と会社が一体となった企業価値向上への取組みが前進しています。全員経営の実現を目指す中、企業価値向上の施策に精通し、多くの経営層と交流を重ねてきた日経BP 総合研究所 ESGフェローの酒井耕一氏と、アズビル株式会社の取締役 代表執行役副社長 横田隆幸が意見を交わし合いました。
自社株を活用して、社員の働く意欲を企業の力に変える
酒井 御社はビルディングオートメーションやアドバンスオートメーションなど計測・制御の技術を通じて、様々な社会課題の解決に貢献してこられました。お客さまに最前線で価値を届ける現場部門と、それを支える本社の両輪で、企業の持続的成長を支えておられるのが印象的です。私はこれまで雑誌記者として、数多くの国内のものづくり企業を取材してきましたが、そこで強く感じるのは「現場」と「本社」の意識のギャップです。例えば、工場では「1銭、1円」の単位で、極めて厳密にコスト管理をしているのに対し、本社はコストに対しては甘いところが見受けられます。本来なら財務面にこそ厳格な規律が求められると考えます。解決策として挙げられるのが、一つには会社自体や経営陣に対する信頼を得るための財務規律を確立することが重要で、それには可視性を高めてガバナンスを強化する必要があります。もう一つは、社員の皆さんにとって「ものづくり」が大切なのはもちろんですが、原資となるお金の重要性についても理解を深めていくことが求められ、そうした意味で自社株は大きな役割があります。ボーナスや昇給には強く関心が向く一方で、自社株の方は、なかなか関心を持ってもらえないのが現状です。これは非常にもったいないと感じていました。そんな中で、御社では従来の社員の自社株保有制度をさらに進化させたインセンティブ・プランを新たに導入されたとのことで、導入自体ももちろん大変だったと思うのですが、それ以上にその価値を社員の皆さんに実感してもらうことの方が、さらに難しい課題ではないかと感じています。その点について、どのようにお考えですか。
横田 おっしゃる通り、社員の皆さんに企業経営の原資となるお金の大切さに目を向けてもらうことは非常に重要です。その理解を深める上で、自社株の保有を通じて社員の皆さんに自分が企業の一員であることをあらためて認識してもらうことは有効だと思います。ただ、株の話を持ち出すと、やはりまだ日本の文化ではなじみが薄いため抵抗感を示す社員も少なくありません。しかし、社員が自社株を持つということは、自分が一生懸命働いた結果が企業価値の向上につながり、それが世の中に評価されたときには株価が上昇し、社員自身がオーナーとしての誇りを持ちつつ、金銭的な価値・喜びを感じられるということです。このような仕組みが整えば、社員のモチベーションが高まっていき、自ら財務面や資本規律にも大きな関心を持って、前向きに企業活動に参加してもらえるようになると期待しています。そうした意味でも私たちはインセンティブ・プラン実現を財務・資本政策に組み込んで、自社株買いを進めてきており、それをどのように社員に還元していくかの検討を重ねてきました。

実感を伴う株式給付制度で社員のオーナー意識を醸成
酒井社員が自らの働きによって企業価値を高め、その成果を報酬として実感できる仕組みとのことですが、そうした考えの下で導入された新たな社員の自社株保有制度について、具体的に教えていただけますか。
横田
まずアズビルで最初に取り組んだ施策は、2017年に導入した「社員株式給付制度(通称:J-ESOP[株式給付型ESOP*1])」です。これは全社員を対象に、給与・賞与に基づいて毎年ポイントを付与し、退職時に蓄積されたポイント数に応じて株式が給付されるという仕組みでした。ところが、この制度には二つの課題がありました。一つは、退職時まではあくまでもポイントとして保有するため「株式を持っている」という実感が持てないこと。そして在職中は配当金を得られず金銭的なインセンティブとしての魅力に欠けていることです。
そこでこの制度を見直し、この4月からは、J-ESOPの改定版となるJ-ESOP-RS*2へと移行しました。ポイントではなく譲渡制限付きの現物株式を給付することで、社員本人が自分名義の株式の保有者となり、議決権の行使および配当金の受取りも可能となります。これにより、社員がオーナーシップを意識し、会社との一体感を持って一緒に成長していける、社員エンゲージメントを通じたWell-beingにつながる新たな仕組みへと進化できたと考えています。
酒井 なるほど。株式を保有しているという、よりリアルな実感を社員に与えることで、会社の業務や経営への参画意識が高まるということですね。
横田
はい。そしてもう一つ、社員が自発的に参加する持株会の仕組みも大きく見直しまして、2022年に「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(通称:E-Ship®*3[持株会処分型ESOP])」を導入しました。この制度では、会社があらかじめ必要な株式を市場からまとめて取得しておき、その株式を、時価で社員に提供します。株価が上昇すれば、その上昇分の恩恵を受けられる仕組みです。もちろん株ですから値下がりすることもあります。しかし、株式取得時の価格から下落した分のリスクは、社員が負担するわけではなく、会社が負うこととなります。つまり、今回のインセンティブ・プランは、通常の持株会で運営している場合と同じリスク(≒保有する株式の時価の下落)を負うのみなので、「得はあっても損はしない」仕組みになっているわけです。
実は今回、この制度をさらに広げていこうと考え、2025年2月に「特別奨励金スキーム」を実施しました。日ごろ、オートメーションでの持続的な社会の発展に向けて頑張ってくれている社員の皆さんへ感謝の気持ちを込めて、社員持株会に加入する社員一人ひとりに40株の株式をプレゼントすることにしたのです。すると、これまで加入していなかった社員からも「それなら加入してみよう」という声が上がり、社員持株会の加入率が一気に高まりました。

全員経営によるグロース戦略と人的資本の強化
酒井 こうした制度の導入によって、社員の皆さんが企業と一体感を持ち、実際に株主としての立場で経営にかかわっていく、これらはまさに「全員経営」を目指した取組みでもあるのですね。米国では、自社株を持った社員が株主総会で意見を述べるという文化があるように、社員でありながら株主でもあるという立場が、経営陣との間に良い意味で対等な関係をもたらしています。そして、これも米国の動向ですが、かつての大手の自動車産業や製薬メーカーなどでは、企業が地域に根差し社員の生活基盤を支える「企業城下町」のような環境の中で、終身雇用に近い形で働くスタイルが一般的でした。これはほかの日本の大手企業においても同様です。そして近年では、こうした長期雇用の価値が米国のIT先進企業でも再評価されつつあります。真面目に働いていれば持株も増えて、株価の上昇も期待できます。その結果、社員にも利益がもたらされ、企業と社員の双方にとっての成長の機会につながるという考え方が広がってきています。こうした成長を重視する考え方は、企業にとっての人的資本の強化につながっていくのです。
横田
アズビルでも同様に、持続的な成長を見据える視点が必要とされています。ご承知のとおり、アズビルの多くのビジネスはBtoB領域で、提供する製品や技術、サービス、エンジニアリングについては、お客さまからも安定的に高い評価を得ています。それは裏を返せば、安定しているがゆえに、変化への対応力や新たな挑戦への意識が希薄になりやすい側面もあります。そのような背景から、2025~2027年度を対象とする新しい中期経営計画は、まさに持続的な成長を強く意識したものとなっており、世の中とともに共創して進化していくことが成長につながるというコンセプトを掲げています。
全員経営に関連した話題としては、大阪・夢洲(ゆめしま)で開催されている大阪・関西万博に協賛していることも一例に挙げられます。若手社員には、自分たちが「興味のあること」や「やりたいこと」を企画しながら、万博のテーマとして掲げられている「いのち輝く未来社会のデザイン」に沿って、ワクワクとした未来像を描いてもらいたいと伝えました。加えて、他社との交流によるコラボレーションを通じて、何かを生み出す体験を、自身の刺激にしてもらいたいと願っています。こうしたすべての取組みが、全員で経営にかかわっていくという意識の醸成につながっていくものと考えています。
外国資本の増加で求められる企業の透明性と財務規律
酒井 そうした中で、企業価値を高めるためのガバナンスの強化についても注目しています。制度面の整備だけではなく、それを支える経営体制そのものの整備も欠かせないと感じています。
横田 十数年前と比べて、外国人株主の比率が高い株主構成へと変化していき、必然的に透明性が高くスピード感のある経営に移行することが求められるようになりました。議論を重ね選んだのが、2022年に行った指名委員会等設置会社への移行です。社外取締役が過半数を占める取締役会と、社外取締役を委員長とする指名・報酬・監査の各委員会を通じて、執行を監督することで、経営の透明性・健全性の向上に努めてきました。
酒井 なるほど。CFOでもある横田副社長が取締役会に参画することで、経営のスピードアップを図られてきたということですね。
横田 はい。指名委員会等設置会社に移行したら、執行役は権限が与えられる代わりにすべて自分たちで責任を負わなければなりません。取締役会は、経営を監督する立場で、いつでも執行役を解任できる権限をお持ちですから、執行役がスピード感と責任感を持って意思決定を行うことで、事業の成長と財務規律の向上につなげていくことが必要だと考えます。
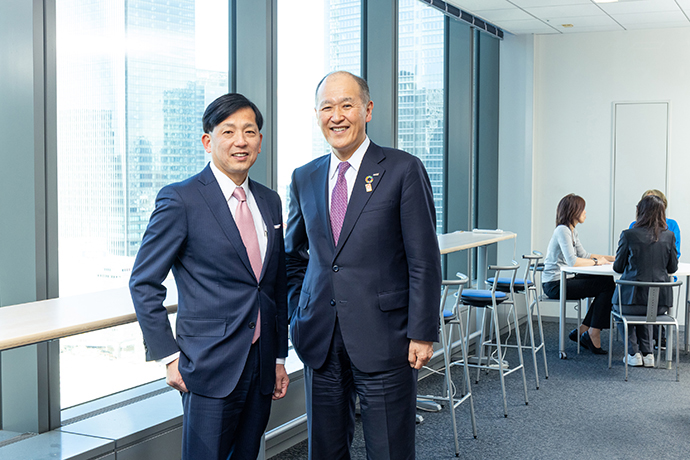
酒井
こうした取組みは、横田副社長ご自身、前職の金融機関において長年にわたりIR活動に携わられており、そこでの豊富な経験があればこそ、各委員会の取締役の皆さんに対し執行側の意図を正しく伝え、説得できたものと思います。
今やビジネスにおける創造性と同時に規律が求められる時代です。それは経営層だけではなく、社員全員に求められてきています。そうした中で、社員の自社株保有制度を通じて社員の方々は、緊張感を持ちながら、一人ひとりが昨日よりも今日、自分が成長したという実感を求めて活動していくことになります。例えば、御社のようなものづくり企業の場合、工場から良い製品を造って出荷したらそれで終わりではなく、仮にそれが売れなければそこで生じる倉庫代や保管代、また減価償却なども意識しなければならない。そうすると、工場で行っていたこれまでの仕事の範囲も拡大してきます。つまり、バランスシートに響いてくるという事実をしっかりと認識しなければならないわけです。
横田 まさに株主になるということは、それらを全部見ていかなければならないということになりますね。自分がやっていることが、会社のプロセスの中で結果としてどういうインパクトを与えるのか、会社の業績や未来にどういう影響を与えるのかを社員が意識する。それが、社員のエンゲージメント向上に非常に有意義に働くわけです。
酒井 そういった意味で社員の自社株保有制度は、このような経営目線を養い、将来的に取締役として会社を支えていく人材育成の基盤にもなり得るのではと考えています。
タレントマネジメントを強化し人的資本を未来へ継承
酒井社員の自社株保有制度の取組みは、社員一人ひとりの人的資本を高める施策の一つということですが、そのほかの取組みについても教えてください。
横田
アズビルにとってサービスやメンテナンス、エンジニアリングがお客さまから高い評価をいただいていることは、既に述べたとおりです。これらを支える社員のノウハウや知見は当社の持続的な成長を支える源泉であり、時代の変化にかかわらず社内で継承していくことが重要です。そのため、AIの活用をはじめとした全社的な取組みにも注力しているとともに、人的資本の強化に向けてタレントマネジメントの視点から議論しています。どこの部署に、どのような人材が、どれだけ必要かといったことも含めて、さらに可視化していかないといけないとは思っています。
私自身、2025年度から人事・教育も担当していますので、こうした人的資本のマネジメントをより実効性のある形に進めていくことが、自分にとっての新たなるチャレンジになると受け止めています。
酒井 本日は、大変有意義なお話をお聞かせいただきありがとうございました。今後のさらなるご活躍を大いに期待しています。
横田 今後もいろいろな場面でアドバイスをいただけると、大変心強く思います。引き続きよろしくお願いいたします。

金融機関での豊富な業務経験をベースに
改革の取組みを力強く牽引してほしい
日経BP 総合研究所
ESGフェロー
酒井 耕一 氏
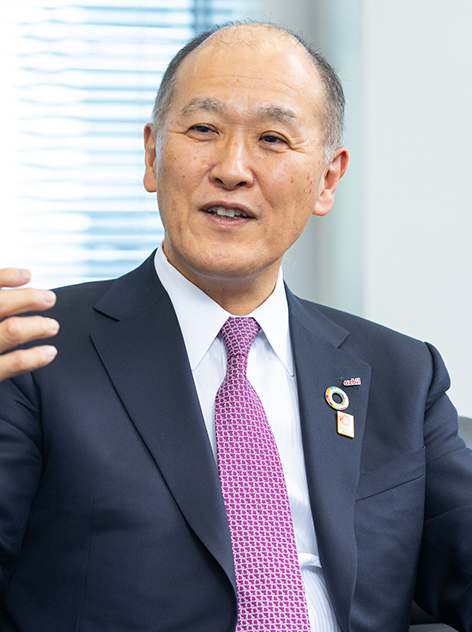
制度改革で挑む人的資本戦略
同じ未来を見て、会社と社員が成長する
アズビル株式会社
取締役
代表執行役副社長
横田 隆幸
- *1:ESOP(Employee Stock Ownership Plan)
企業が拠出する金銭を原資に自社株を取得し、受益対象者である社員にインセンティブとして自社株を給付する仕組み。 - *2:J-ESOP-RS(Japanese Employee Stock Ownership Plan- Restricted Stock)
一定期間の譲渡が制限された普通株式を社員に割り当てることで、株主と同じ目線に立ちながら、持続的な企業価値向上を図るインセンティブを社員に付与することを目的としている給付制度。 - *3:E-Ship®(Employee Shareholding Incentive Plan)
米国で普及している従業員持株制度ESOPを参考に野村證券株式会社と野村信託銀行株式会社が開発したもので、社員持株会の仕組みを応用した日本初の社員向けインセンティブ・プラン。

 関連情報
関連情報





