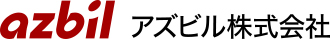働き方改革
働き方改革
働き方改革から働きの創造へ:働きやすい環境整備
社員が活き活きと自分らしく働くことができるようにするためには快適で働きやすい職場環境が必要との考えから、新型コロナウイルス環境下における在宅勤務を起点として、これまでの働き方改革を「働きの創造」(働く環境の整備と学習する機会の提供)へと発展させ取り組みを進化しています。ハイブリッド勤務(在宅並びに出社やリモート勤務を組み合わせて働くこと)とあわせてリモート勤務でも生産性を落とさず業務に取り組めるようDXによる業務改革を推進するほか、出社時には新しいオフィス環境を社員に提供すると同時に、社員一人ひとりの繋がりを高める様々なコミュニケーション施策(社長他経営層が自ら国内外のazbilグループ社員と対談を行う機会を設け、自由闊達な双方向でのコミュニケーションを行うとともに、その内容を社内ホームページ等で共有することで繋がりを高めているほか、社内コミュニケーションツールの充実やメンター制度、短期の他部署へのインターン制度等)を進めることで、社員のWell-beingとエンゲージメントの向上に努めています。
総労働時間の削減に関する考え方
「働き方改革」は健康で活性化され生産性の高い職場を作り、過重労働をなくし、社員がワークライフバランス(仕事と生活の調和)を充実させることを目的としています。会社と社員が持続的に発展し続けるためには、業績だけではなく、「日々仕事に取り組む社員が心身の健康を保ち続けること」が重要と考えています。
その考えのもと、社長を本部長とする『働き方対策本部』を設置し、長時間労働の削減方針として労使で締結している36協定を遵守し、1ヵ月の残業時間45時間超過者ゼロ名を目標に掲げ、各事業の担当経営及び部門長が自ら陣頭指揮し「仕組み」「人員」「制度」の切り口で取組みを進めてきました。現場作業のバックオフィス化、業務効率向上のための各種システム改修、新規ツール導入や、お客様・現場の時間にあわせた柔軟な勤務ができるよう勤務制度の見直し、繁忙部署への応援、人員補強など、様々な取組みを通じて改善が進み、1ヵ月残業時間45時間を超える社員数の減少につなげることができました。
こうした残業削減、ワークライフバランスの充実を文化として根付かせるため、毎週水曜日と金曜日を「ゆとり創造の日」と称して定時退社日としたり、有給休暇取得奨励日を設けたりするほか、職場の業務改善活動について、随時、自薦、他薦で表彰を行っています。また、不適正な残業申告にならないようにするための取組みとして、全社メッセージの発信、アンケート等の実施、人事部において個別のフォローを行うほか、システム面でも、全事業所への入退室時刻、社員のパソコンの稼働時間を把握し、適正な労働時間申告を促す仕組みを整えています。
労働基準監督署からの臨検を受けるなど、労働基準に関する監査を受けており、2024年度に臨検を通じて是正指導を受ける事象は生じておりません。
また2024年度は、自社の労働基準に対するコンプライアンス違反もありませんでした。
心身ともに健やかな生活の実現
社員の健康管理
私たちは、健幸宣言にあるとおり、社員一人ひとりの健康が企業活動の重要な基盤であると考え、『からだの健康づくり』と『こころの健康づくり』を、各拠点の安全衛生担当部署、azbilグループ健康保険組合、産業保健スタッフ、職場のマネジメント層、労働組合、人事部門が連携しながら推進しています。
『からだの健康づくり』では、社員の健康増進を目指して、肥満や生活習慣、健康診断結果、職場環境調査の結果を分析し、取り組むべき課題を明確にしています。具体的には、各種のがん、糖尿病、高血圧、肥満などの生活習慣病や、新型コロナウイルスや結核などの感染症といった、さまざまな健康問題に対する対策として、健康教育や健康診断、がん検診、予防接種、病気になった社員の職場復帰支援プログラム、治療と就労の両立支援プログラムを提供しています。
さらに、『こころの健康づくり』においては、メンタルヘルスを強化するために、上司が部下の変調に気づくためのラインケア研修を継続的に実施しています。さらに、ストレスチェックの結果で高ストレスと判定された社員には、産業医との面談を通じて個別にケアを行い、早期発見と予防に努めています。復職後の再発を防ぐため、休業から復職する際には必ず復職プラン検討会を開催し、復職の時期や業務計画を確認します。復職後も産業医による継続的なフォローアップを行い、社内で相談しにくい場合には、外部EAP機関を活用した社外メンタル相談窓口も設けています。
ハラスメントのない職場づくり
毎年定期的に全社員に実施しているコンプライアンス意識調査の結果に加え、社員満足度調査の結果やストレスチェックの集団分析結果も併せて分析、評価し、職場のマネジメント層と人事部で対策の検討を進め、職場環境に改善に取り組んでいます。
また、上記の調査結果を踏まえ、ハラスメント発生リスクをより一層低減させるためのマネジメント教育を実施しています。
2021年度からは継続教育としてグループ会議等を通じて所属長から展開することで、ハラスメントの定義や具体的な事例に学びながら、ハラスメントの無い明るく活性化された職場づくりを推進してきました。2024年度には、全社員を対象としたLMS教育を実施し、理解の浸透と意識の向上を図っています。
CSR教育を通して、万一ハラスメントが発生した場合の相談窓口として社内・社外ともに匿名でも対応可能な「なんでも相談窓口」を周知しています。